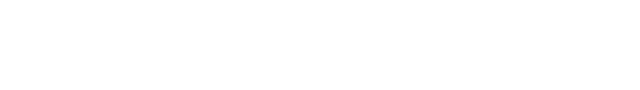【子どもの溶連菌感染症】症状・診断・治療・登園の目安まで徹底解説✔
溶連菌感染症とは?
子どもが急に高熱を出し、喉が赤く腫れる症状が見られた場合、それは溶連菌感染症かもしれません。
溶連菌は風邪と似た症状を引き起こしますが、細菌感染であるため適切な治療が必要です。
本記事では、
- 溶連菌感染症の症状と診断方法
- 治療法と登園・登校の基準
- 合併症や家庭での注意点
について詳しく解説します。
1. 溶連菌感染症の原因と感染経路
溶連菌(溶血性連鎖球菌)は、主にA群β溶血性連鎖球菌によって引き起こされる細菌感染症です。
特に2歳~15歳の子どもに多く見られますが、大人も感染することがあります。
感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」です。
- 飛沫感染:くしゃみや咳で飛んだ細菌を吸い込む
- 接触感染:感染者が触れたおもちゃやドアノブを介して広がる
流行の時期は、特に冬季(11月~3月)と梅雨時期(6月~7月)です。
2. 溶連菌感染症の主な症状
代表的な症状は以下の通りです。
- 38℃以上の高熱
- 喉の痛み(強い咽頭炎)
- 扁桃腺の腫れと白い膿(白苔)
- 舌が赤くブツブツする(イチゴ舌)
- 発疹(猩紅熱)
- リンパ節の腫れ
咳や鼻水が少ないのが特徴的です。
潜伏期間は2~5日間です。
3. 溶連菌感染症の診断方法
迅速検査キットを使い、喉の粘膜を綿棒でこすり取って検査します。
結果は約15分で判明します。
検査が陰性でも症状が典型的な場合、医師の判断で治療を開始することもあります。
4. 溶連菌感染症の治療法
溶連菌感染症は細菌感染症なので、抗菌薬による治療が必須です。
- 第一選択薬:ペニシリン系(アモキシシリンなど)
- ペニシリンアレルギーがある場合:セフェム系やマクロライド系
- 服用期間:10日間しっかり飲み切る(途中でやめると再発や合併症のリスクあり)
自然治癒は難しいため、適切な治療を受けましょう。
5. 登園・登校の基準
厚生労働省の学校保健安全法では、溶連菌感染症は「条件付きで出席停止」の対象です。
- 抗菌薬を服用開始後24時間経過し、
- 熱が下がり、体調が良ければ登校可能
保育園や学校によっては治癒証明書が必要な場合もあるので、事前に確認しましょう。
家庭での感染予防には、手洗い・うがいの徹底、こまめな消毒が重要です。
子供と違い大人には出勤を制限する規制はございません。
6. 溶連菌感染症の合併症に注意
抗菌薬を適切に服用しないと、以下の合併症を引き起こすことがあります。
- リウマチ熱(関節炎や心疾患を引き起こす)
- 急性糸球体腎炎(血尿やむくみ)
- 劇症型溶血性連鎖球菌感染症(まれだが重症化しやすい)
抗菌薬を飲み始めて3日以上経過しても改善しない場合は、再受診しましょう。
7. まとめ
✅ 溶連菌は適切な治療で改善する!
✅ 抗菌薬は必ず10日間服用する!
✅ 登園・登校は抗菌薬開始24時間後からOK!
✅ 合併症を防ぐため、異常があればすぐ受診!
お子さんの体調に不安がある場合は、お気軽に当院へご相談ください。