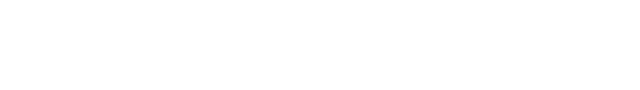9ヶ月目の赤ちゃん
ハイハイがとても上手になってくる時期です。後追いをしてどこにでも移動してくる赤ちゃんが多くなります。離乳食も3回になり、だんだんと栄養を食事からとるようになってきます。運動機能では個人差がとても大きく出る時期です。不安なことは9〜10ヶ月検診の時にしっかりと担当医にお話しましょう。
目次
1・この時期の身体的・心理的特徴
2・9〜10ヶ月検診
3・離乳食の後期
4・9〜11ヶ月目までのワクチン接種
1・この時期の身体的・心理的特徴
ハイハイが上達して、下半身の筋肉が発達することで、不安定ながらにつかまり立ちを始める赤ちゃんも出てきます。お手てをパチパチしたりバイバイがしっかりとできるようになり、なんでも大人の真似をし、褒めてあげると何度もやるようになります。ママやパパへの後追いが激しくなる時期で、おトイレまでついてきて、見えなくなると泣いてしまう赤ちゃんもいます。自我が芽生えだし、オムツ替えを嫌がったり、両手を広げて抱っこして欲しいと意思表示をするようになります。指の動きも発達して、この頃になるとカップや哺乳瓶を自分で持って飲むようになります。また、ストローから飲めるようになる赤ちゃんも増えてきます。
ますます好奇心が芽生えて体の機能も伴ってきますので、大人が「まだ大丈夫」と思っていても、ちょっとした引っかかりから立ち上がってしまったり、物を取り出してしまったり、思わぬ行動が突然できる時期でもあります。くれぐれも赤ちゃんのいるところ、仮に立ったときに手が届くところなど十分に注意して、危険なものから遠ざけるようにしましょう。
2・9〜10ヶ月検診
9〜10ヶ月検診では主に運動機能の発達をみます。おすわりが完成しているか、ハイハイの様子、つかまり立ちの様子などを調べます。体を倒した時に両腕を広げてバランスをとろうとするか(パラシュート反射)の確認もします。
この時期にハイハイをせず、お尻で移動する赤ちゃんもいますし、移動すら抱っこをせがむ赤ちゃんもいます。検診で足の関節などの異常が見られない場合はそのまま様子を見ましょう。伝い歩きを始めてから行動的になる赤ちゃんもいます。
3・離乳食の後期
いよいよ毎日3回の離乳食が始まります。この時期には栄養の5〜6割を離乳食からとるようになります。この時期のお悩みで多いのが、好奇心も増してきているため、食べむら、遊び食べなどなかなか思うように食べ進めてくれないということです。お腹が空いていたら自然と食べるようになるので、様子を見ながら進めていきましょう。離乳食のスタートが遅かった赤ちゃんは焦らず、2回食を食べるようになり、ある程度のかたさのある食べ物をもぐもぐと食べられるようになっていれば3回食に進んでみましょう。
栄養面のこともしっかりと考えていきたい時期です。特に鉄分の多いレバー、赤身肉、マグロやイワシ、大豆製品、ほうれん草、小松菜など意識して取り入れるようにしましょう。赤ちゃんが食べる食べないは、いつも同じではありません。眠たいときやぐずっているときはいつものようには食べてくれません。そんな時には柔らかさを変えてみたり、形状を変えてみたりするのもいいでしょう。
4・9〜11ヶ月目までのワクチン接種
これまでの接種状況を確認しましょう。通常のスケジュールですと以下の接種が完了していると思います。
- ヒブ(3回)
- 小児用肺炎球菌(3回)
- B型肝炎(3回)
- ロタウィルス(2回または3回)
- 四種混合I期(3回)
- BCG(1回)
接種漏れがある場合には1歳までには終わらせましょう。気になることがあればお医者さんに相談しましょう。
- インフルエンザワクチン(任意)
インフルエンザは毎年10月〜12月の間で年に2回、1回目の接種から2〜4週間後に2回目を接種しましょう
身体的特徴や離乳食の進み具合、この時期は大きな個人差があるということを知っておいてください。周りの同じ月齢の子の様子と比べて焦る必要は全くありません。少しでも気になることがあれば、信頼できる小児科医に相談しましょう。
当院では、小児科専門医、アレルギー専門医、呼吸器専門医、総合内科専門医が在籍しています。そして医師たちは育児中のママさんでもあります。お気軽にご相談ください。
当院はじめての方へ
当院には、小児科専門医、アレルギー専門医、呼吸器専門医、総合内科専門医、が在籍しています。
小児から大人への一貫したアレルギー診療が可能です。
高い専門性を有しながらも一般的な内科・小児科の診療も可能です。
在籍医師は育児中の女性医師です。ワクチン接種時や乳幼児健診や診察時など育児に関することもお気軽にご相談ください。
当院の受診方法は?
風邪をひいた、せきが長引く、便秘、肌がかさかさする、発熱、風邪(かぜ)、咳(せき)、鼻水・鼻づまり、のどの痛み、下痢・嘔吐、腹痛、頭痛、中耳炎、ひきつけ(けいれん)などの症状など多岐にわたる小児科一般の病気を診断・治療しています。
小児予防接種、乳幼児健診、お子様の諸症状でご心配の場合には、小児科専門医・アレルギー専門医・呼吸器専門医・総合内科専門医が在籍する当院へ気軽にご相談ください。
ご予約について
待ち時間状況、時間帯予約はこちら
(当日の時間帯でのご予約が可能です。直接のご来院も可能ですが、予約優先となります。)
小児科・アレルギー科・呼吸器内科・内科・院長ブログもよろしければご覧下さい。
その他よく読まれている記事は?
【小児科・アレルギー科】小児の気管支喘息(ぜんそく)について
花粉症対策ガイドページを公開致しました
患者様が花粉症対策の情報を探しやすいように、花粉症対策のガイドページを作成しました。役立つ情報もあると思いますので、是非ご覧ください。
咳・喘息のページを公開致しました
患者様が咳に関する情報を探しやすいように、咳や喘息のガイドページを作成しました。役立つ情報もあると思いますので、是非ご覧ください。
取材記事について
女医に訊く!2020年4月号
「アレルギーはどうして起こるの?花粉症対策」について、取材協力致しました。
日経DUAL 2020年 12月号
ママパパ向け年齢別記事 「保育園」
「注意したい子どもの3つのせき 特徴と受診目安は?」について、取材協力致しました。
🤒インフルエンザB型大流行中🤒
お子さんから大人まで、インフルエンザBが流行っています
学級閉鎖の学校も出ていますね💦
A型、B型で対処の方法は変わりませんが、受診される患者さんは嘔吐、下痢を伴う方が多く、高熱が続き脱水になるお子さんもいらっしゃいます。
☑️水分、塩分、糖分を摂取しましょう
☑️ぐったりしたらすぐ受診してください
☑️おしっこの濃さやお通じの様子も確認してくださいね
自身が罹るともちろん辛いですが、お世話するご家族も大変だと思います
看病でわからないことがありましたら、是非看護師にご質問くださいね🏥
#インフルエンザ
#アレルギー
#ハピコワ
#ハピコワクリニック五反田
#五反田
#咳
#小児科
#子供
#呼吸器内科
#品川区
#大崎
#アレルギー科
#花粉症
#喘息
#咳喘息
小児科医師が増えました✨👩⚕️👨⚕️✨
9月より毎週金曜、土曜は東邦大学医療センター大森病院の小児科医師が勤務しています👶👧🧒🩺
みんな優しく、元気な先生です♪
外来中にはなかなかお伝えしきれない担当医師のこと、看護師が真心込めて書きましたのでぜひ読んでみて下さいね😊
風邪、便秘、長引く咳
どうぞ当院小児科をお役立てください🏥
#スギ花粉
#鼻水
#くしゃみ
#鼻詰まり
#眠気
#舌下免疫療法
#アレルギー
#ハピコワ #ハピコワクリニック五反田 #五反田 #クリニック #小児 #小児科 #呼吸器 #呼吸器内科 #品川 #品川区 #大崎 #アレルギー科
#花粉症 #喘息 #咳喘息 #インフルエンザ #予防接種 #花粉症 #スギ花粉症 #ハピコワくみちゃんねる
📣YouTube始めました📣
吸入薬……それは吸入の仕方に効果が左右される、奥の深いお薬です🫁
薬局やクリニックで吸入の仕方を聞いて、いざ自宅でやってみると…
…
…
…これ、吸えてるの…?
ハピコワクリニック五反田では、ご自宅でのそんなご不安を少しでも軽減出来るよう、YouTubeで吸入方法をお伝えしています😊
是非参考にしてみて下さいね✨👩⚕️
👉https://youtube.com/@user-ld5yl8su3s
#スギ花粉
#鼻水
#くしゃみ
#鼻詰まり
#眠気
#舌下免疫療法
#アレルギー
#ハピコワ #ハピコワクリニック五反田 #五反田 #クリニック #小児 #小児科 #呼吸器 #呼吸器内科 #品川 #品川区 #大崎 #アレルギー科
#花粉症 #喘息 #咳喘息 #インフルエンザ #予防接種 #花粉症 #スギ花粉症 #ハピコワくみちゃんねる
🏥6月1日開院🏥
田町に呼吸器内科クリニックを開業します👨⚕️🩺
田町駅徒歩1分、三田駅からは0分の場所です。
長引く咳、咳喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)など、お困りの方にお役立て頂ければ幸いです。
ハピコワクリニック五反田、田町三田駅前内科呼吸器内科アレルギー科、どちらもよろしくお願いします!
診療予定表はお手数ですが、各医院ホームページをご参照くださいませ。
田町院 https://tm-naika.jp
五反田院 https://hapicowa-clinic.jp
#田町三田駅前内科呼吸器内科アレルギー科
#スギ花粉
#鼻水
#くしゃみ
#鼻詰まり
#眠気
#舌下免疫療法
#アレルギー
#ハピコワ #ハピコワクリニック五反田 #五反田 #クリニック #小児 #小児科 #呼吸器 #呼吸器内科 #品川 #品川区 #大崎 #アレルギー科
#花粉症 #喘息 #咳喘息 #インフルエンザ #予防接種 #花粉症 #スギ花粉症 #